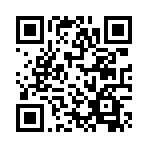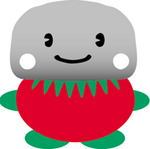2009年05月29日
焼津の魅力第5弾!
「焼津祭り」
焼津神社の例大祭は二基の神輿が市中を神幸します。
二基の神輿は焼津独特の「アンエットン」の掛け声と共に
白装束の担ぎ手に舁き上げられ、時に勇ましく
海道一の荒祭りとも呼ばれ、市中は祭り一色に彩られます。
屋根の神紋色、金の巴紋が先輿、銀の巴紋が後輿と呼ばれ、
先輿には主神の日本武尊、後輿には相殿神の
吉備武彦命・大伴武日連命・七束脛命の三柱の神の
御神霊をお遷ししています。後輿はいかなることがあっても
先輿を追い越すことはないそうです。

私も小学生の頃から参加しています!
焼津神社の例大祭は二基の神輿が市中を神幸します。
二基の神輿は焼津独特の「アンエットン」の掛け声と共に
白装束の担ぎ手に舁き上げられ、時に勇ましく
海道一の荒祭りとも呼ばれ、市中は祭り一色に彩られます。
屋根の神紋色、金の巴紋が先輿、銀の巴紋が後輿と呼ばれ、
先輿には主神の日本武尊、後輿には相殿神の
吉備武彦命・大伴武日連命・七束脛命の三柱の神の
御神霊をお遷ししています。後輿はいかなることがあっても
先輿を追い越すことはないそうです。

私も小学生の頃から参加しています!
2009年05月29日
焼津の魅力第4弾!
「かつお」
焼津は現在、全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。
焼津と鰹の歴史はたいへん古く、今から1400年余以前の弥生時代にまでさかのぼります。
その当時、焼津一帯の集落の人々が米食をし、鰹を獲って食べていたことが証明されたのです。
それは、焼津神社周辺の「宮の腰遺跡」から発掘された遺物に端を発しています。
この遺跡から土器類や剣・鏡・曲玉などの土製模造品、米などの食糧品に混じって魚の骨片が出土。
そして、その骨片は考古学者の鑑定によって“かつお”の骨であることが分かりました。
このことからも焼津は、大昔から“かつお”と切っても切れない縁の深い町であることがうかがえます。

焼津は現在、全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。
焼津と鰹の歴史はたいへん古く、今から1400年余以前の弥生時代にまでさかのぼります。
その当時、焼津一帯の集落の人々が米食をし、鰹を獲って食べていたことが証明されたのです。
それは、焼津神社周辺の「宮の腰遺跡」から発掘された遺物に端を発しています。
この遺跡から土器類や剣・鏡・曲玉などの土製模造品、米などの食糧品に混じって魚の骨片が出土。
そして、その骨片は考古学者の鑑定によって“かつお”の骨であることが分かりました。
このことからも焼津は、大昔から“かつお”と切っても切れない縁の深い町であることがうかがえます。

2009年05月29日
焼津の魅力第3弾!
「なると巻」
なると巻の起源ははっきりと分かっていませんが、1864年にまとめられた
「蒟蒻(こんにゃく)百珍」という書物にすでに記述があります。
なると巻の最大の産地は焼津市で、国内で消費されるなると巻の9割を作っています。
焼津でなると巻の製造が始まったのは、大正末期のこと。
それ以前にもなると巻は使われていましたが、一般化したのは、
日本でラーメンが普及した昭和初期からです。
以来、なると巻の需要は着実に増え続け、「なると巻成形機」や「水封式蒸し機」が開発され、
大量生産に結びついていきました。

なると巻の渦巻きのいわれとしては、無限・成長・生命のシンボルとしてや、
鳴門(なると)海峡(かいきょう)の渦潮に似ているからなど諸説あります。
練り製品であるなると巻は、れっきとしたかまぼこの仲間。そして純粋な日本生まれの食品です。
目に楽しく食べておいしいなると巻は、お料理に味と色のアクセントを添えます。
なると巻の起源ははっきりと分かっていませんが、1864年にまとめられた
「蒟蒻(こんにゃく)百珍」という書物にすでに記述があります。
なると巻の最大の産地は焼津市で、国内で消費されるなると巻の9割を作っています。
焼津でなると巻の製造が始まったのは、大正末期のこと。
それ以前にもなると巻は使われていましたが、一般化したのは、
日本でラーメンが普及した昭和初期からです。
以来、なると巻の需要は着実に増え続け、「なると巻成形機」や「水封式蒸し機」が開発され、
大量生産に結びついていきました。

なると巻の渦巻きのいわれとしては、無限・成長・生命のシンボルとしてや、
鳴門(なると)海峡(かいきょう)の渦潮に似ているからなど諸説あります。
練り製品であるなると巻は、れっきとしたかまぼこの仲間。そして純粋な日本生まれの食品です。
目に楽しく食べておいしいなると巻は、お料理に味と色のアクセントを添えます。
2009年05月29日
焼津の魅力第2弾!
「黒はんぺん」
江戸・明治時代までは、駿河湾を漁場とする漁師の家では、もとは、
いわしやサバなどの魚をそのまま自家用にして食べていたそうですが、
その後、すり鉢ですってお湯に入れて加工して食べるようになったといいます。
これが黒はんぺんの始まりとも言われています。300年以上の伝統を持つ
静岡県焼津市の郷土色豊かな食品です。地元焼津では黒はんぺんのことを
「はんべ」とも呼び、大変ポピュラーな食材です。

黒はんぺんは、サバやいわしを原料として、独自の製法で職人さんによって作られます。
うまみたっぷり。白はんぺんよりも魚のうまみが濃厚です。魚丸ごと骨まで練りこんで
作られているため、カルシウム・ミネラル・鉄分・ ビタミン・DHA(ドコサヘキサエン酸)・
EPA(エイコサペンタエン酸)などが豊富に含まれています。
私は、20歳になるまで白はんぺんの存在をしりませんでした・・・
江戸・明治時代までは、駿河湾を漁場とする漁師の家では、もとは、
いわしやサバなどの魚をそのまま自家用にして食べていたそうですが、
その後、すり鉢ですってお湯に入れて加工して食べるようになったといいます。
これが黒はんぺんの始まりとも言われています。300年以上の伝統を持つ
静岡県焼津市の郷土色豊かな食品です。地元焼津では黒はんぺんのことを
「はんべ」とも呼び、大変ポピュラーな食材です。

黒はんぺんは、サバやいわしを原料として、独自の製法で職人さんによって作られます。
うまみたっぷり。白はんぺんよりも魚のうまみが濃厚です。魚丸ごと骨まで練りこんで
作られているため、カルシウム・ミネラル・鉄分・ ビタミン・DHA(ドコサヘキサエン酸)・
EPA(エイコサペンタエン酸)などが豊富に含まれています。
私は、20歳になるまで白はんぺんの存在をしりませんでした・・・